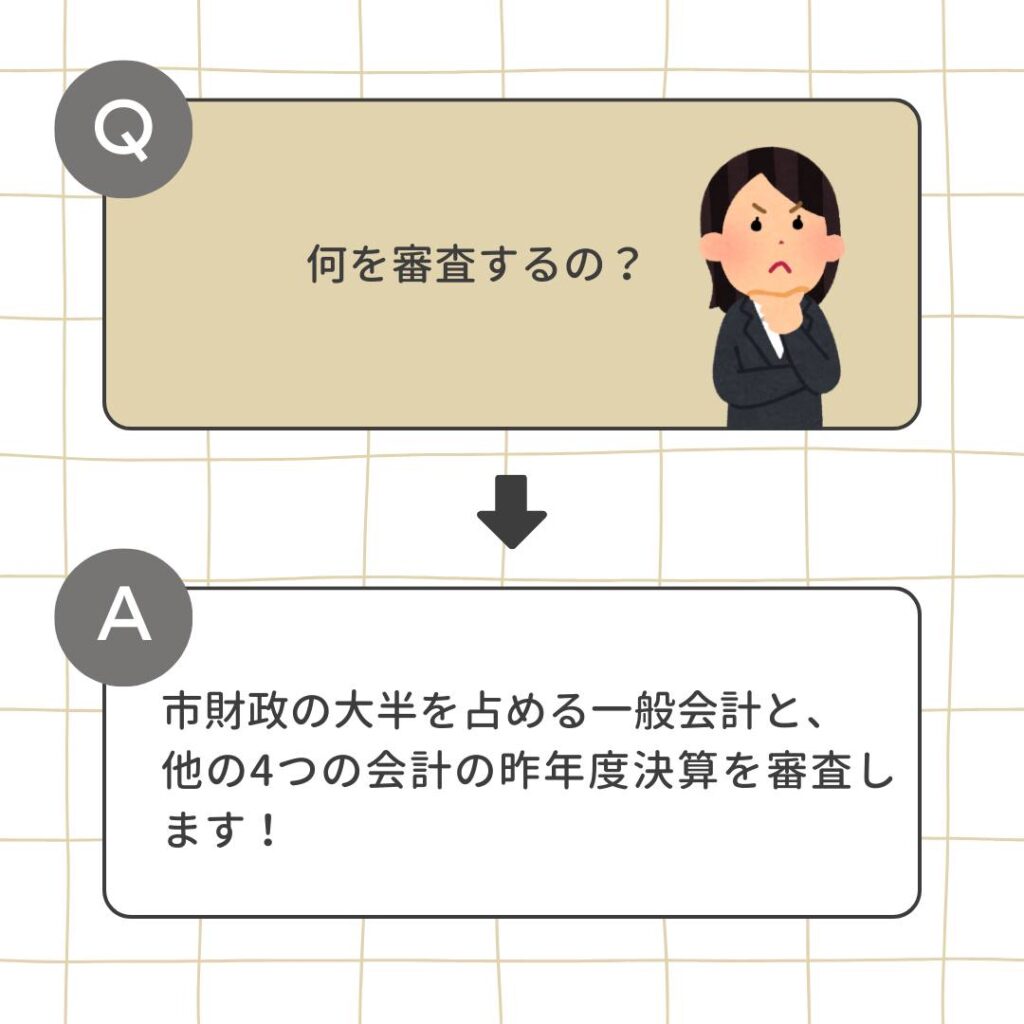
本日の決算特別委員会4日目、夕方に一般会計の質疑が全て終了したので、明日は討論(賛否とその理由を述べる)を、決算認定に反対の会派、賛成の会派、反対の会派、賛成の会派…の順で行い、採決を図ります。
その後、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の3特別会計、下水道の順で審査、採決し、5日間の委員会は閉会となります。
議会としての結論は、10月3日の9月定例議会最終日に、決算特別委員会に所属しなかった議会選出監査委員(村山じゅん子議員)と私(副議長)も加わった上で採決を図り、確定させます。
そして、決算の確定を踏まえ、議会閉会後に市長は速やかに来年度予算編成方針を公表し、具体的な留意点を記した副市長名での「依命通達」が発出され、2月初旬に向けて予算編成作業が一気に動き出すというサイクルになっています。
➡令和7年度の予算編成がどのように進められたかは市HPのコチラからご覧いただけます。
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/gyozaisei/gyozaisei/yosan/zaisei20241003.html
今年も10月第2週には、「令和8年度予算」というページが登場するはずです。
前市長の時代(平成18年まで)は、決算特別委員会は9月議会閉会後の10月~11月に開催されたので、決算の確定は12月議会初日でした。つまり、議会の意思や意向を次年度予算に反映させるつもりはなかった、ということになります。
右肩上がりの頃は、予算に比べて「終わったこと」である決算は軽んじられていたのは、全国的なことでしたが、「それではいけない」と気づいた自治体から、予算編成に入る前に決算を確定させる流れになりました。
東村山市議会でも決算委員会の委員は、その頃までは全議員のほぼ半数で済ませていたことも、決算軽視を体現していたと思います。
また、議会において示された会派の見解を市長サイドが尊重する義務は制度上ありません。増してや表舞台である議会ではなく、会派要望という形で議会の外で市長に対して賑々しくあれこれ求めるのが全国的に当たり前のようになっていますが、それこそ本来は何ら制度的裏付けのない行為です。
議会が本来行うべきことは、決算審査を通じて明らかになった課題を、たとえ1点でも2点でもよいので議会内で共有、合意した上で、議会として附帯決議なり附帯意見なりの統一見解にまとめ上げ、市長に対して次年度予算編成に反映させることを求める、ということです。
「決算 附帯決議」とか「決算 附帯意見」と検索してみると、多くの議会で必要に応じて行っていることがわかると思います。会派や会派に属さない議員ごとに己の見解「討論」を述べるに留まっている東村山市議会は、まだまだ未熟な議会であることを認めざるを得ません。
