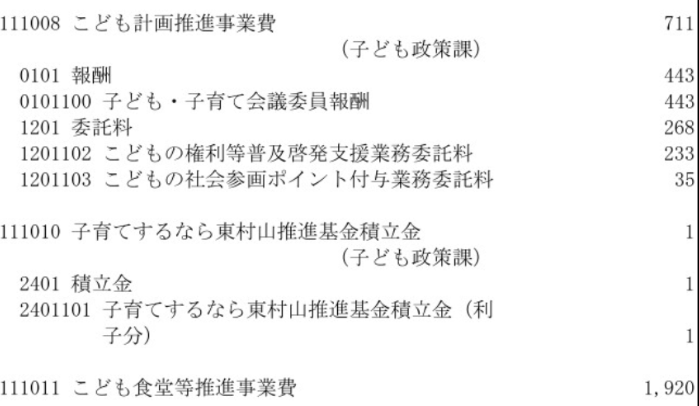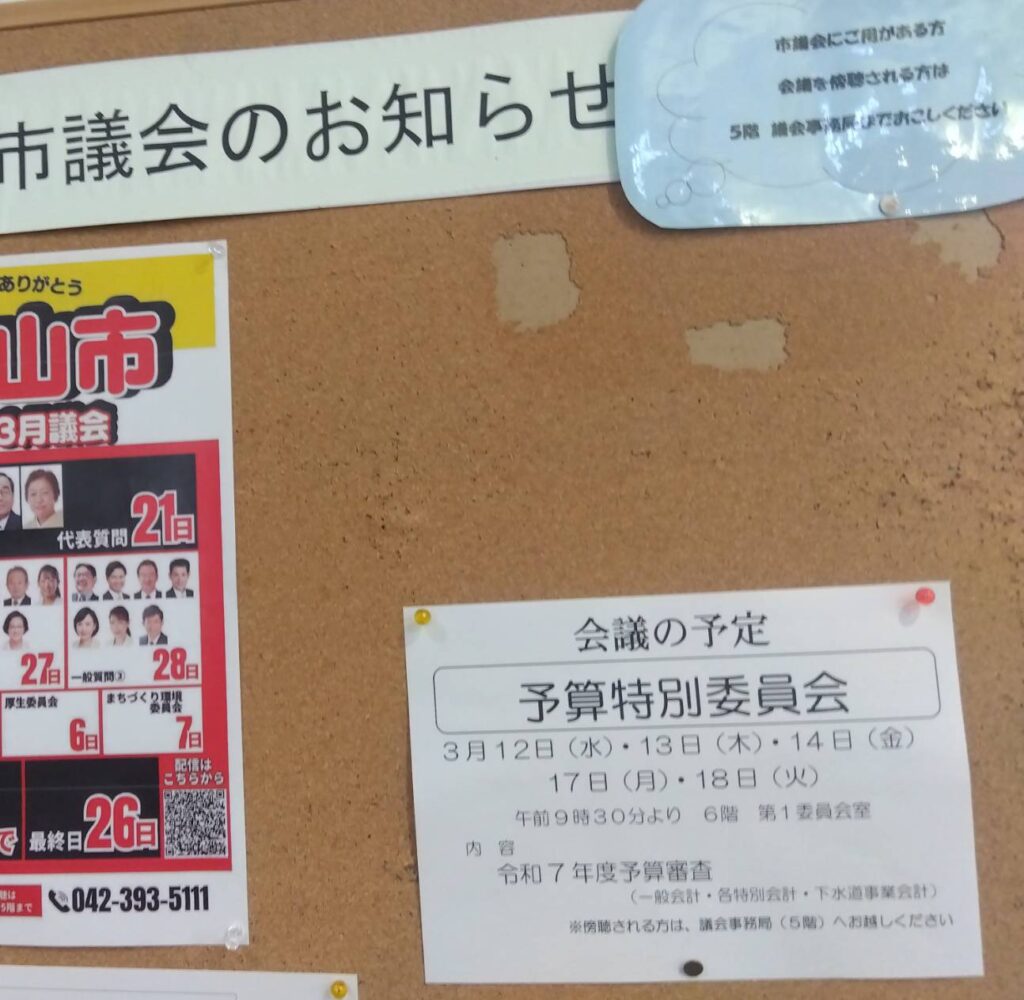今日(12日・水)から2025年度予算案の審査を行う予算特別委員会が始まりました。大きなトラブルが無ければ、13日(木)14日(金)17日(月)18日(火)の計5日間の予定です。
初日の今日は、総額697億2904万円の一般会計予算案について、総括的質疑を(※以下、敬称略)小林美緒(自民)、伊藤真一(公明)、渡辺みのる(共産)、朝木直子(草の根)、かみまち弓子(立憲民主)、佐藤まさたか(無会派)、白石えつ子(無会派)、鈴木たつお(無会派)、わたなべたかし(無会派)、かくたかづほ(無会派)の順に質疑を行い、続いて歳入部分の質疑を小林、伊藤と終えたところで、続きは明日9時半から、となりました。
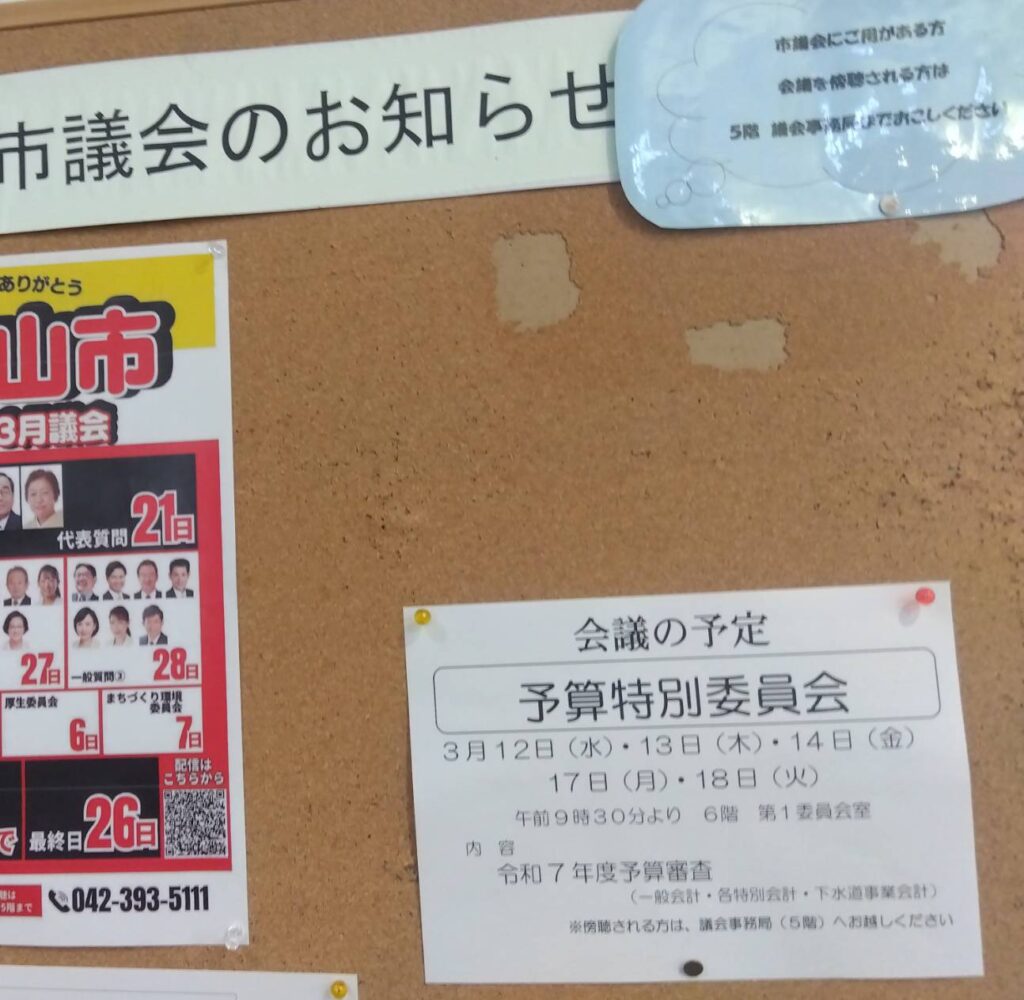
自分が発言するためには、私の場合は少なくとも先行する5人のやり取りをちゃんと聞いていないと、うっかり同じ点を取り上げてしまったり、深掘りするための視点を聞き逃したりしてしまうので、真剣に聴いてないとなりません。
午前中は小林議員、伊藤議員、渡辺議員と、各会派のエース級が並んだので、聴きごたえがありました。小林議員と伊藤議員の総括に関する質疑と答弁をメモが取れた範囲で以下アップしてみます。とはと言っても、こんなに克明にメモを取ることは珍しいんですけどね(^^; あくまでメモなので参考程度にお願いします。間違いあると思います。
尚、自分の発言はメモを取る余裕などないので、思い出すのがとても大変です。
【小林美緒議員 発言メモ】
《総括の質疑》
Q.総括して伺う。
財政課長)臨時財政対策債がゼロ、賃上げ増による税収増、連動交付金増で11億6千万円の一般財源増。49億増えたが財調繰入額は減とするなど、持続可能な財政、投資的経費も確保。まちづくりへ。
Q.先行き不安あると感じる。一般会計規模の伸び率が高い特徴的な要因は?
A.学校給食費無償化、薬師山緑地、テニスコート人工芝改修、中小企業支援等の支援。国庫財源を伴う事業費の増が顕著で、児童手当や生活保護等国庫支出金は22.9%の伸び…全国平均は8%台だが当市では伸びが大きい。
Q.国都の交付金膨らんでいるが、一般財源を必要とする事業も増えているのか?
A.国庫支出金を伴う増が主な増。DX、公園取得、公共施設改修、7年度は定額減税調整給付金や児童手当などで過去最大。性質別は物件費の伸びが顕著…DX推進に係る経費は、導入時は国費だったがランニングは一般財源。光熱水費、委託料などで物価高騰の影響受けた。扶助費増の要因にもなっている。予算規模は増加傾向で、一般財源を必要とする事業も増えているが、基金の活用などで予算編成に努めて来た。
Q.スマートスクールに伴う財源負担や物価高騰で物件費や扶助費を押し上げていること理解した。臨財債ゼロになったが見解と今後の見込みは?
A.地方税収の伸びなどで13年度以降初めて発行ゼロ。総額は1,600億円減額。国の計画ほどの税収増は当市では見込めないので、総額減の影響は厳しさ増す要因となった。しかし税連動交付金、枠配分などによって予算確保する一方で、財調繰入額は抑制できた。地交税の大幅減額はないと見込むが、その後は何も決まっていない。
Q.臨財政ゼロと物価高騰はカバーできたとわかった。改革で予算に反映された面は?
企画政策課長)事業分析の上で展開図り、効果を発現させ、持続可能な行財政運営必要。課題の解消目指す事業としては、企業立地促進事業がある。地域経済循環率が低いという課題に対応した改革の名にふさわしい取り組み。
Q.枠配分編成による乖離、苦労、部内間での調整、当初の重点政策は
財政課長)所管要求との乖離は、1件査定ではなく各部で行うことで財源配分ができた。もともと裁量が少ない、予算が小さいところは苦労したと聞く。各部で主体性持って見直し進めた。次長職中心に調整し、財政課も入って。企業立地、女性活躍推進、デジタルワンストップの運用、萩山公園整備。行財政改革の視点では、生成AI活用、会計事務、照明LED等…
Q.理事者側からの事業の提案はあるのか?
A.所管からの要求の中に指示があったものが含まれているとは思うが、確認していない。
Q.性質別歳出で、給与改定に関する財源は?
A.国の地方財政対策として給与改善費2,000億円確保されている。
Q.中心核の整備…久米川駅から八坂駅までのグランドデザインは?
まちづくり推進課長)都市計画マスタープランの考えがベース。商店街のデザインまとめる。7年度は駅前広場設計、地域とのワークショップ等を重ねて進めていきたい。
Q.戸越銀座に行ったが、負ける気しないなと思った。道路劣化も酷いという声もあるので対応を。闇バイト強盗増により、都が防犯カメラ補助打ち出している。
防災防犯課長)7年度から2か年間の補助実施。都からまだ詳細来ていないが、早い段階での実施に向けて準備しており、4月1日の市報や市HPで周知する。
【伊藤真一議員 発言メモ】
《総括の質疑》
Q.地方財政対策と市財政、予算編成の取組み。給与の考え方。見込まれる人件費増への計画は。
財政課長)7年度の対策では予め一般行政会費の給与改善費として2,000億円。
Q.国はデジタル活用推進事業債の起債を認めている。充当率は90%、紹介財源の50%は卒地される。活用は?
A.デジタル活用推進事業債が創設された。当初予算では見込んでいないが、今後国から詳細が示されたら必要に応じて活用考えたい。
Q.枠配分方式について。
A.厳しい状況改善するために各部での事業見直しを加速させる目的から、事務事業見直しの一環で導入した。生み出した財源活用できるので、進むことを期待している。
Q.部別削減目標と金額は継続的に可能なのか?
A.7年度の効果は、累計額15億円で一定の成果。今後も持続可能と見込んでいるが、市民ニーズの変化などで引き続き状況に応じた柔軟な調整が求められる。
Q.インセンティブで時間外手当削減と言うが効果は?
A.2,400時間、677万円を見込んでいる。
Q.職員のコスト意識はどう変化したのか?
A.例年は財政課が行っていたことを自ら行うことで、財政的な視点で振り返ることは大きな変化。同様の意見ももらっている。さらなる調整見直しが図られてこれから発言する効果にも期待。
Q.実質単年度収支の黒字の確保、プライマリーバランスの実現を志向していると考えるが、本来あるべき手法と考えるが市長の考えは?
市長)10年ぶりに導入。課題もある。健康福祉部のような部署は効果の発現は限界があり、苦労している。電気料や印刷料など他部にまたがる経費を抱えている部も難しい。意図せずに市民に迷惑かけるリストラや再構築が行われる可能性もあり、トップダウンが細部まで行き届かないという制度上の課題はある。効果は、累計15億円ほど調整したことで、財調繰入金が2.3億円減等の効果あった。職員一人ひとりがコスト意識や事業の優先順位を考えたので、繰り返していけば組織全体によい効果を生むと考える。しかし万能ではないので、制度上の課題をどうクリアしていくか、執行や決算見ながら改善図るべく8年度予算の編成にも落とし込んでいきたい。8年度以降の世界経済、日本経済、参院選、税制改正等、大きな課題があり、8年度編成は相当不透明な中でスタートするので、枠配分でどこまで対応できるのかよく考えながら対応すべく検討してきたい。
Q.財政調整基金残高への見解
財政課長)標準財政規模10%を目安にしているが、7年度末見込みは大きく下回ると予測。依然として財政運営は厳しい。残高確保を目指したい。
Q.基金残高確保も視点に入れて執行を。6年度と7年度の充当一般財源は?
A.7年度は356億円。6年度は345億。11億6,100万円、3.4%増。
Q.4年や5年度比べると厳しいね。真水財源の状況。
A.6年度比で26億4,700万円の増。7年度の増は市町村総合交付金の割合が大きい。これは実質的に特定財源と位置づけているが、真水部分が増えることは望ましい。
Q.臨財債の皆減となりながら、真水増となっていることの見解は?
A.実質的な地方交付税の減額は当市において厳しさを増す要因となった。結果として、税連動交付金の伸びなどで予算確保できた。
Q.中長期的には望ましい方向なのかな、と思う。ひと息ついた感があるが、中長期的にはどういう見通しか?具体的な数値を上げて説明を。
A.中長期的見通しの段階よりも僅かだが上向いていることは事実。7年度中に8年度以降の財政フレームを示す。
Q.7年度は国の施策と皆さんの努力でやや好転してきたように見えるが、大きく変化したわけではなく、国の動向に左右されるので、基金の確保と事業見直しを。
Q.事業別評価シートの改善は?
企画政策課長)7年度版は2つ改善した。①施策が目指す姿欄の追加:どこを目指しているのか明確にした。課題と表記していた欄を、達成に向けた本事業の課題、と変えた。②成果指標の変更:過度なコストや負担を生じないことを前提として検討し、成果指標⇒成果を測定するための指標 と修正した。
Q.活用の課題と効果は?
A.PDCAのDからCへの過程にある。6年度決算以降は、計画段階と結果を並べることになる。説明責任を果たすことが目的だが、決算年度のよく
Q.3日年度掛かる予算と決算の悩ましい課題はどこの自治体でも。総合計画事業の進捗管理が主眼となっているので、総合計画審議会で行うべきではないのか。
経営改革課長)おっしゃる通り、制度設計は行革審で行ったが。適切な見直しが行えるよう考える。