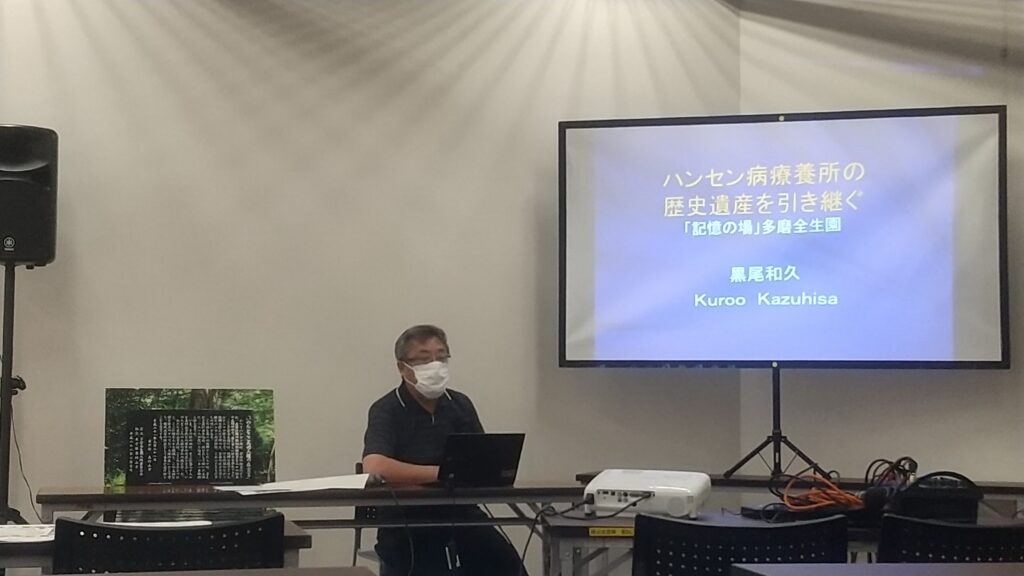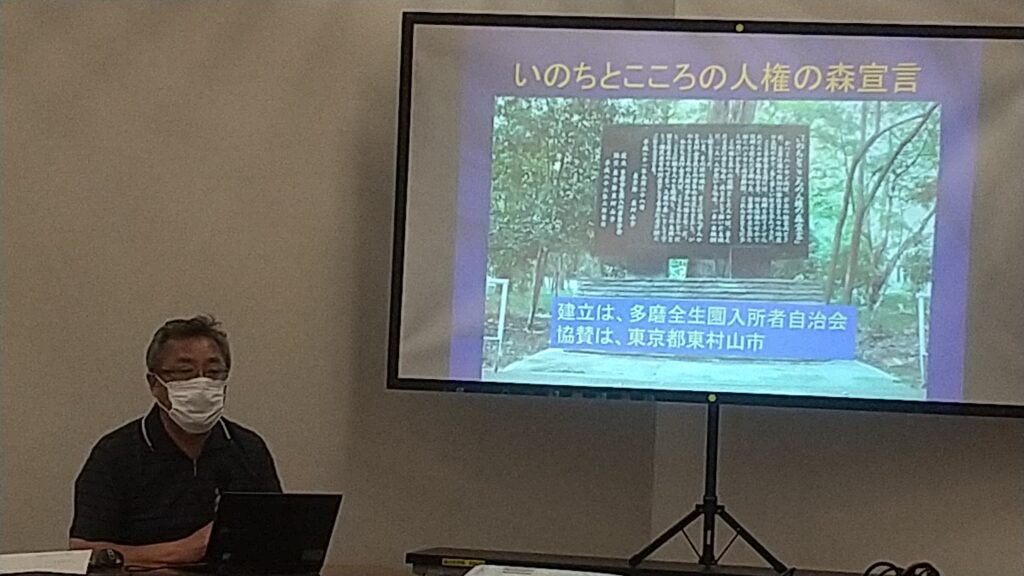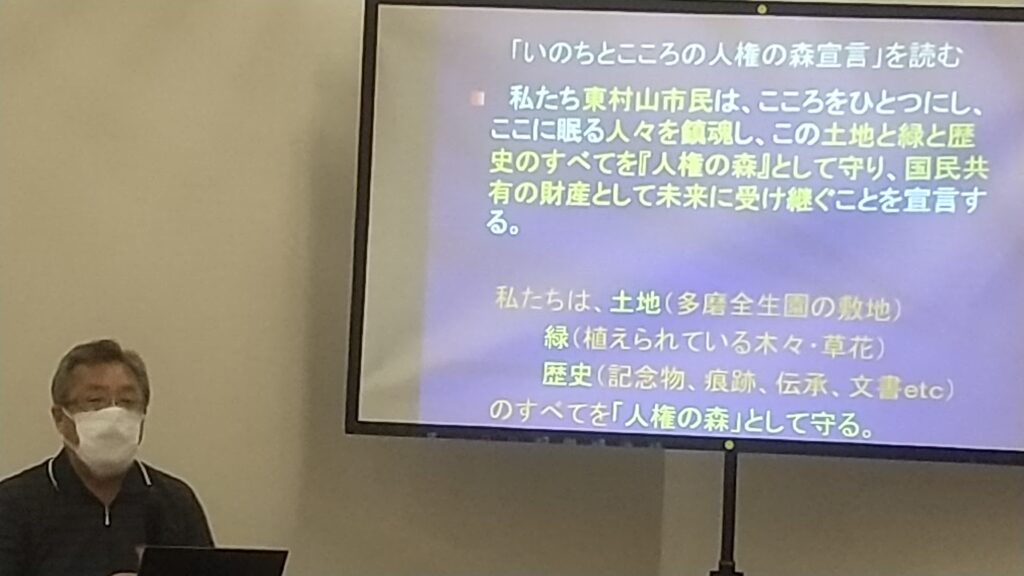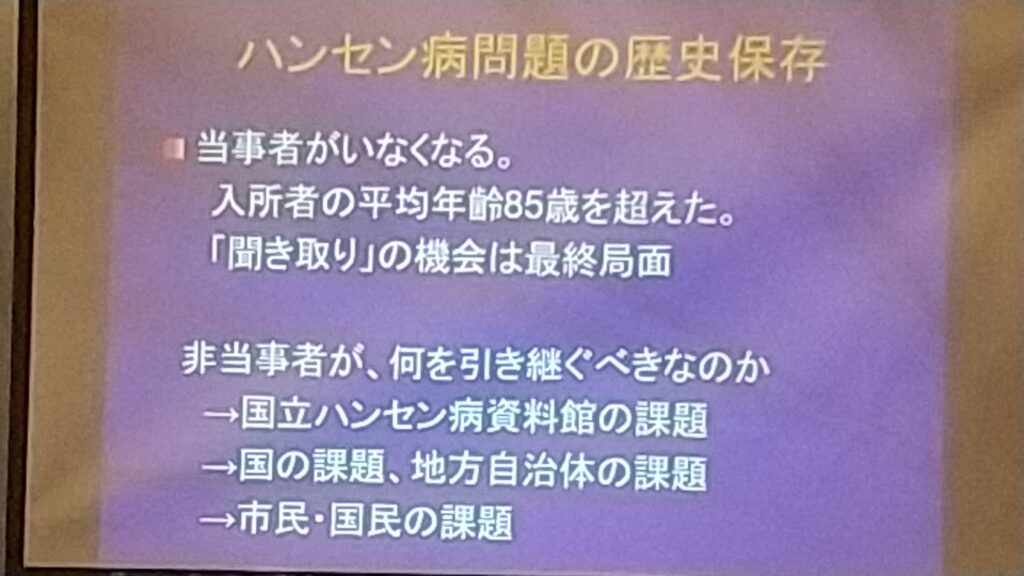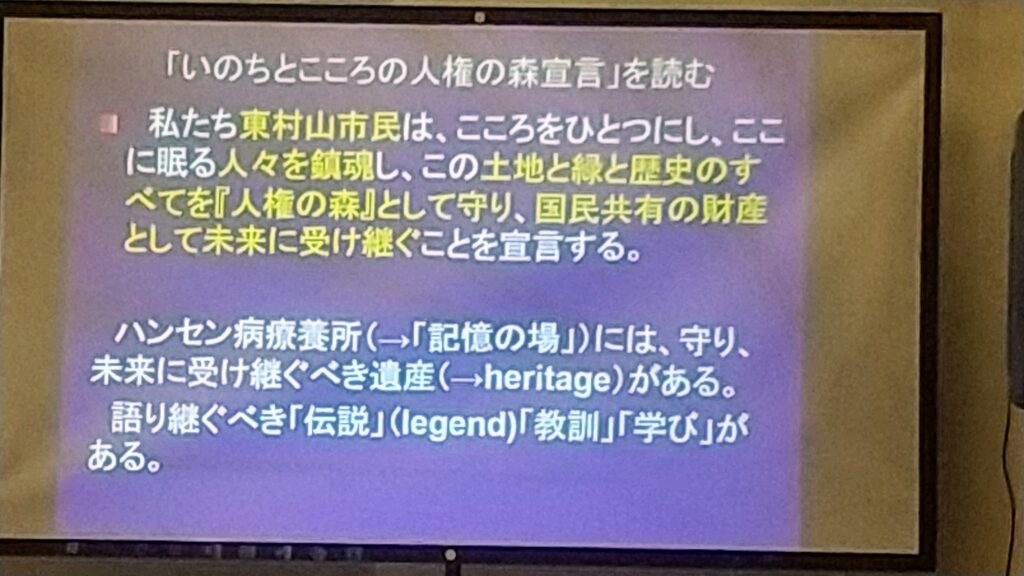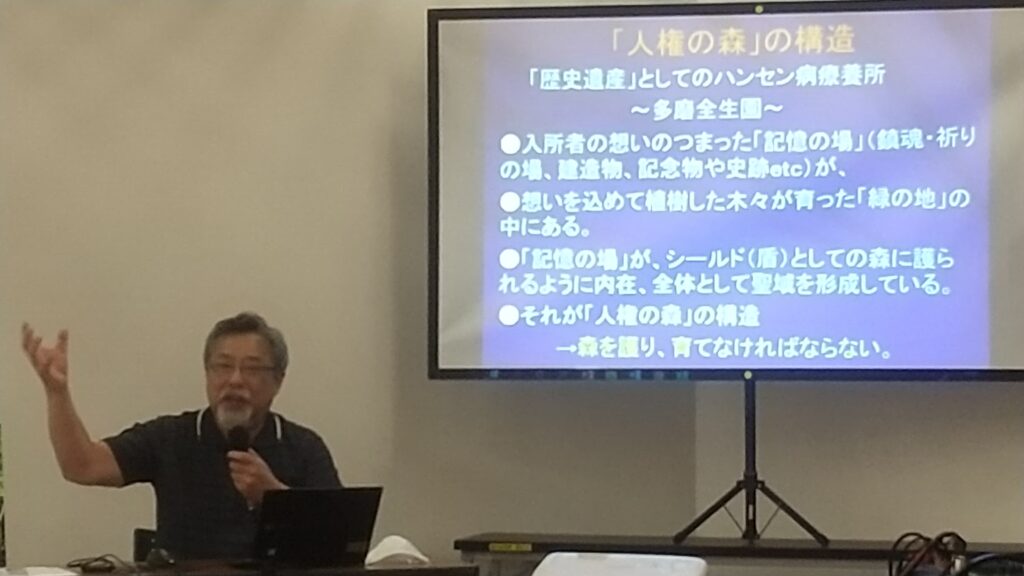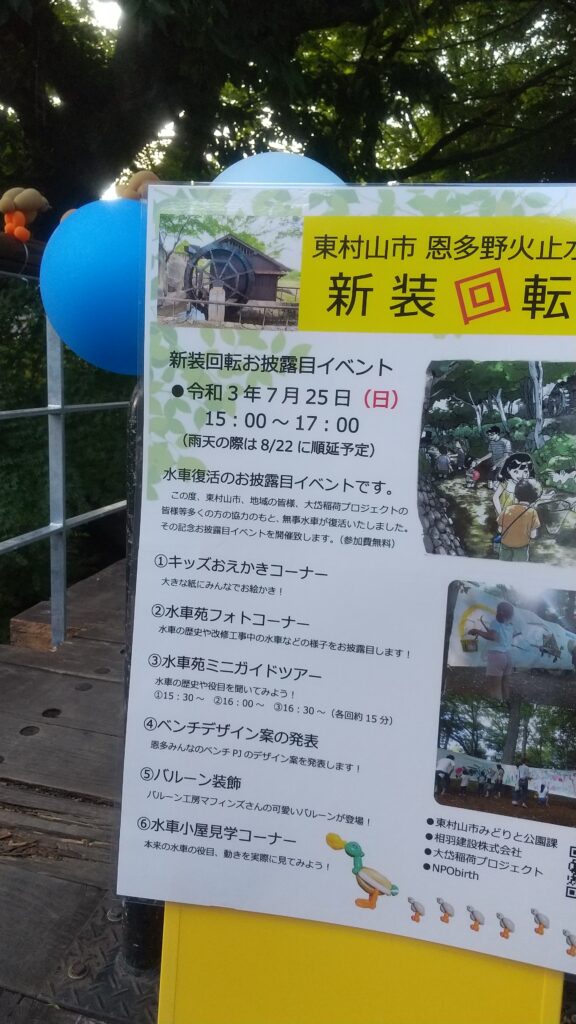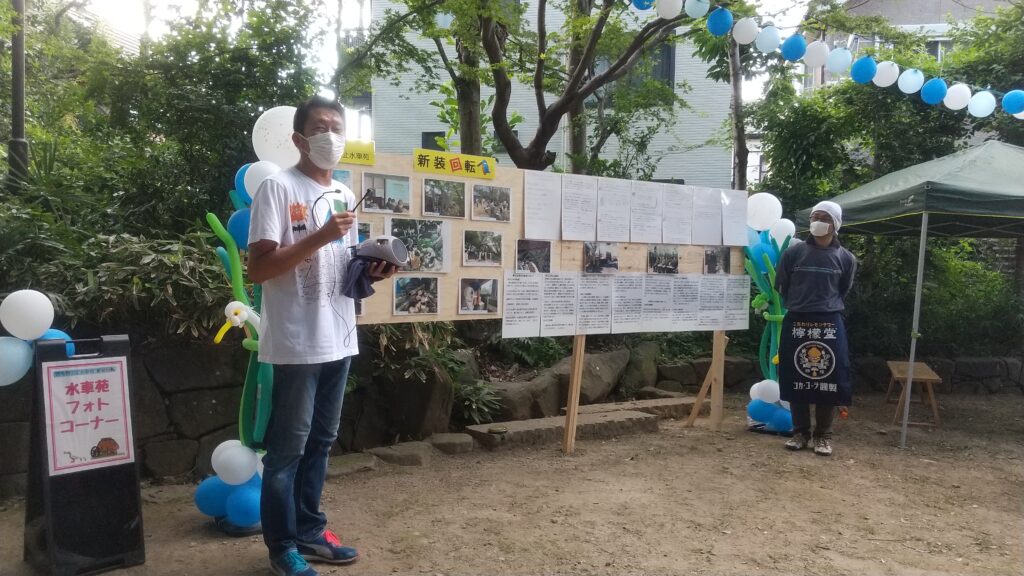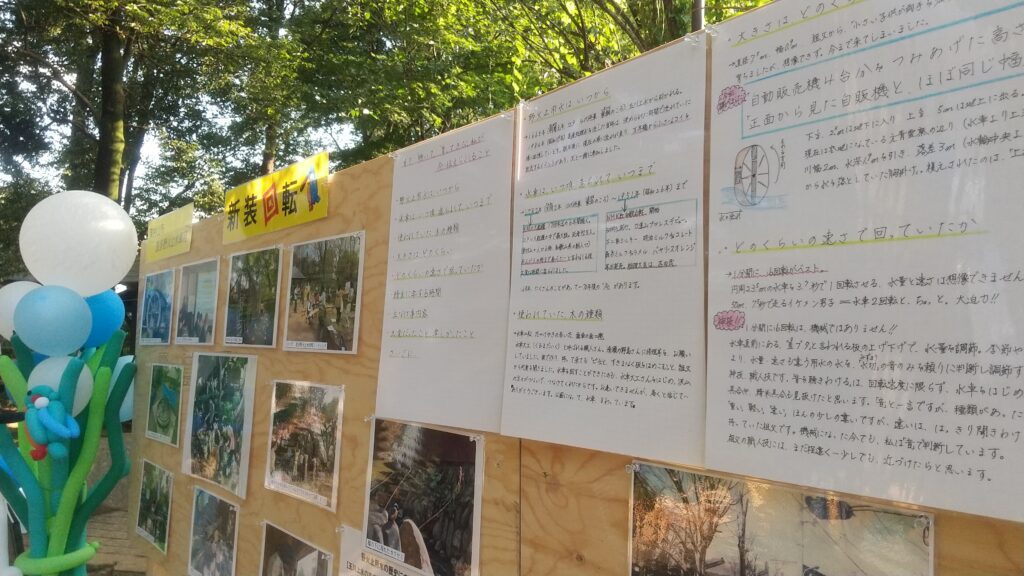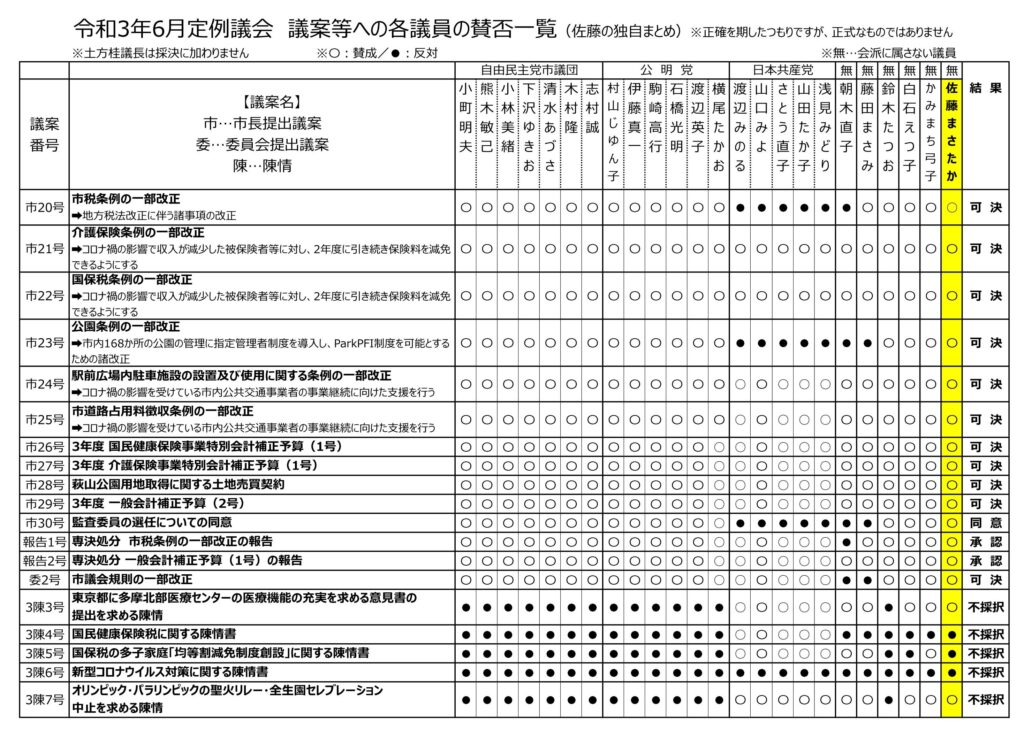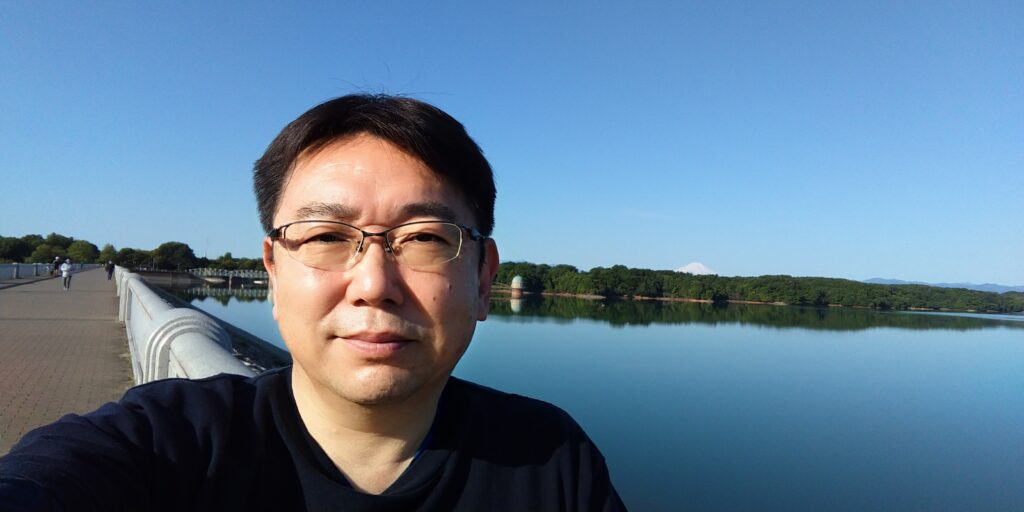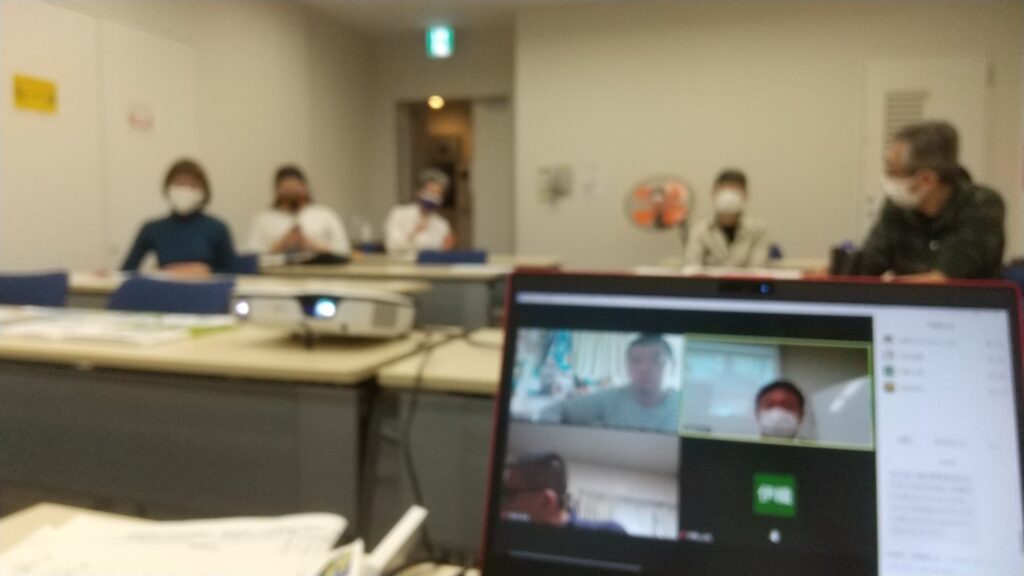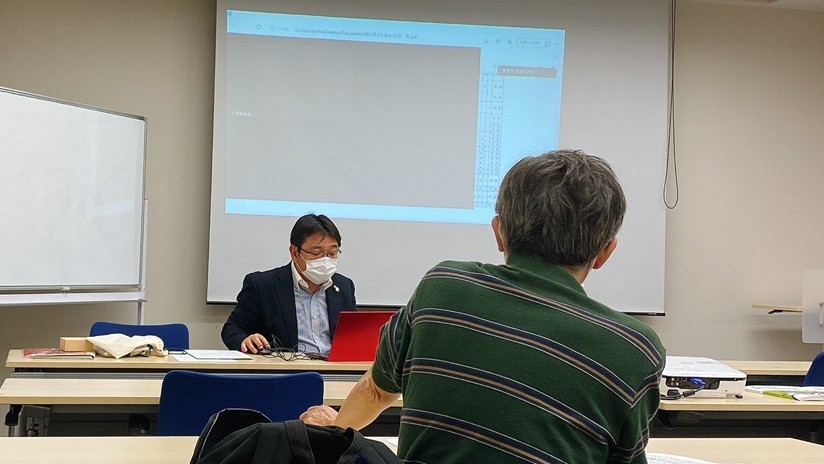1日8人×3日間の一般質問の2日目が終わりました。
明日10時からの3日目は、私から始まり、鈴木たつお議員までが順に質問に立ちます。
私が今回取り上げるのは次の2題。
1.市民の命を守るため、市として新たに取り組んでほしいコロナ対策
2.自然も人もまちも元気になる公園づくりを実現するために
大きな1点目は、新型コロナ対策です。
「保健所がないので市には情報が無く難しい」とされてきた「自宅療養者の支援策」に急いで取り組むべきだ、とまず求めるつもりです。
質問通告書を提出した8月20日には国立市、武蔵野市、小金井市の3市のみが取り組んでいましたが、2週間足らずの間に各市のHPから対応が確認できないのは、東村山市を入れて3市のみ、という状況になっています。
確かに未だに保健所からは「誰が感染しているのか」という情報は市には全く伝えられていませんし、感染症法では国や都が行うべきことと基礎自治体が行えることには明確な役割分担がある、という所管部長の答弁も筋論としてはわかりますし、長い間にわたって休日返上状態で変遷する課題処理に取り組んできた市職員の大変さも十分理解するところです。
それでも、その上で、各市が「感染して自宅療養となっている方は市に連絡をください。3日分の食料とパルスオキシメーターを届けます」という対応に踏み切ったのは、自分のまちに暮らす市民に対する責任を果たそうとするものだと思います。「市民の命を最優先」を新たな総合計画の冒頭に掲げた東村山市としても、とにかく一刻も早く実行に移してほしい、そう考えています。
さらに、「PCR検査体制の拡充」と「子どもの感染拡大への対応」についても、質問します。
10時ちょうどから質問に立ちますので、お時間があったら★ネット配信★をご覧いただければと思います。
通告してある質問内容を以下、画像とテキストでアップします。

1.市民の命を守るため、市として新たに取り組んでほしいコロナ対策
感染拡大から1年半を超え、課題が刻々と変遷する中、全庁挙げての対応を重ねて来られたことに感謝申し上げたい。その上で、過去最も厳しい状況を前に、基本構想冒頭で「市民の命を最優先に施策を展開します」と明記した自治体として、取り組みの拡充を求め、以下伺う。
1)自宅療養者の支援を
①自宅療養者への支援拡充は、東京都に強化を求めると共に、市として緊急的に取り組むべき重要な政策と考える。当市同様に保健所を持たない国立市や武蔵野市で実現しているのはなぜか。どのような事業スキームで行われ、成果を上げているのか。
②感染で苦しむ市民の不安を受け止め、少しでも小さくしていくために、相談窓口の開設と、できる支援に至急乗り出していただきたい。考えを伺う。
2)PCR検査の拡充を
①症状がある方が検査を受けたくても受けられないという声は届いているか。検査を行っていることを公表している市内のクリニック等はいくつあるか。小平保健所管内の他市の状況はどうか。
②清瀬市と共同開設したPCRセンターの最近の利用実績はどうなっているか。
③市内のクリニック等で検査ができる体制を医師会に要請して作っていただきたい。考えを伺う。
3)子どもの感染拡大への対応を
①保育所や児童クラブに加え、夏休み中の小中学生に感染が広がっている現状をどう分析しているか伺う。
②2学期の開始と共に感染拡大が起こることが大変懸念される。希望する中高生へのワクチン接種を加速させることも必要と考える。市長部局と教育委員会ではどのように学校での感染防止を強化していくのか伺う。