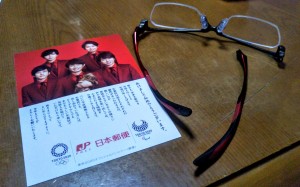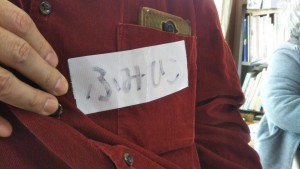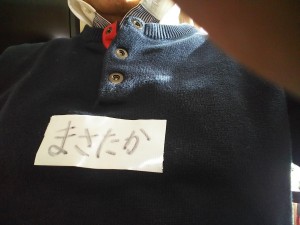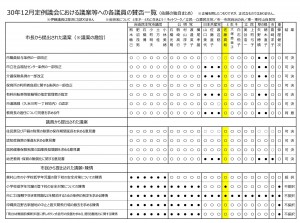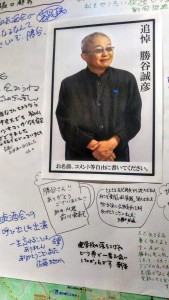2月3日(日)未明、「きよっぴー」こと、母・佐藤清江は84歳7か月の人生を全うし、旅立ちました。

 ひ孫の奏太と
ひ孫の奏太と
2月1日(金)の朝から意識が薄らぎ、握り返すことも少なくなり、酸素マスクの音だけが部屋に響くようになりました。
でも、生後9か月になる孫の大きな声には首を揺すって応え、殆ど反応しなくなっていた土曜日の午前中には、うちの次女が「童謡を歌う会」の皆さんの歌声をLINEライブ中継したら唇を動かし涙を浮かべていました。間違いなく届いていたと思います。
 トレードマークの割烹着姿で
トレードマークの割烹着姿で
4きょうだいで宿直を決めて、結果的に最後の夜となった土曜日は、私が母の隣でエキストラベッドに寝ていました。4時10分過ぎにアラームが鳴ると、それまで安定していた心拍数が急降下し、間もなく呼吸がゼロになり…。最期はipodからお友達たちの歌声が耳元で流れる中、心臓が静かに止まったようです。
 去年の母の日日本語
去年の母の日日本語
ずっと元気印できた母。
30年以上のお付き合いだった童謡の仲間、ここ10年続けてきたオカリナの会の仲間、そして私たちが団地っ子だった40年も50年も前からお世話になった近所の八百屋さん、酒屋さん。
誰もが、「人の世話ばかりしていた」「頼りにしていた」「いつも笑っていた」「人を悪く言うのを聞いたことがない」「大好きだった」等と口々に言ってくださいました。
また母はよく、お彼岸には大量のあんこを、春には大ぶりイキのよい筍を毎日のように煮ていました。
そのほとんどは、所属する会の仲間や隣近所や孫たちに届けるために。
「おいしいって食べてくれるのが一番うれしいのよ!」が母の口癖でした。
背骨の圧迫骨折で入院したはずが、想定外のことが続いて一気に内臓が弱ってしまったことは、どこかで何かが違っていたら…と思わずにいられない面がありますが、笑顔で生きてきた母には繰り言は似合わないね…と弟たちと。
私の電話で駆けつけた親族は、子と孫(その夫&妻)、曾孫まで合わせて24人。
生後9か月も19日目のBabyも、おばあちゃんの最期の輪の中にいました。
 昨年10月の甲府デートにて
昨年10月の甲府デートにて






命はこうして受け継がれていく。
母はそのことを人生をかけて伝えてくれたように思います。
4年近く先にあちらへ行ったじいちゃんは結構めんどくさいけれど、久々の再会を大好きな黒ラベルで乾杯して楽しんでくださいな。
あなたの息子に生まれてこられて幸せでした。
おつかれさまでした。ありがとう。
息を引き取ってから今日で5日目が終わろうとしています。
いつかこういう日が来ることは避けられませんが、次々と訪ねて来て、「どうして…」「なぜ急に…」「私よりずっと元気だったじゃないの…」「いつものように笑ってちょうだい」「あなたがみんなの面倒を30年みてくれたから私たち頑張ってこられたのよ…」等々と泣き崩れる長年のお友だちを見て、今はまだ死なせてはいけない人だったのだ、なぜあの時に連れて帰らずに入院を選んでしまったのだろう…と母にも周りのすべての人にも申し訳ない気持ちでいっぱいになっています。
生前時折そうしていたように、母の眠る部屋の隣のリビングに座布団並べて横になり、弟たちと交代で宿直さんをしてきました。母は静かに穏やかに眠っていますが、毎日「おばあちゃん、ただいま!」と子も孫もひ孫も帰ってきて、にぎやかにご飯を食べたりおしゃべりをしたりして、母との最後の時間を楽しんできました。
こういう時こそ長男はやるべきことをちゃんとやれ、という父の言葉が聞こえるので、母が何の心配もしないで次のステージでも栗ご飯を炊いてあんこを煮て大好きなおせんべいを配って…たくさんの笑顔が届けられるよう、ちゃんと送ってやりたいと思います。
お別れの場を教えてください、とご連絡をいただきました。当初は家族で送ろうかと思っていましたが、現役真っ最中に急逝した母に、最後にもう一度会いたいと言ってくださる方が大勢いることがよくわかりましたので、できる範囲でお知らせをしています。
明日8日(金)の午後3時過ぎに、自宅から母を送り、斎場へ向かいます。
通夜は8日(金)18~19時、告別式は翌9日(土)13~14時。
会場はいずれも日野自動車正門前の東都アールホールです。
土曜日はちょうど雪が降る時間と重なるのではないかと案じていますが、お越しいただける方は、どうかお気をつけていらしてください。
お世話になった皆さま、本当に本当にありがとうございました。
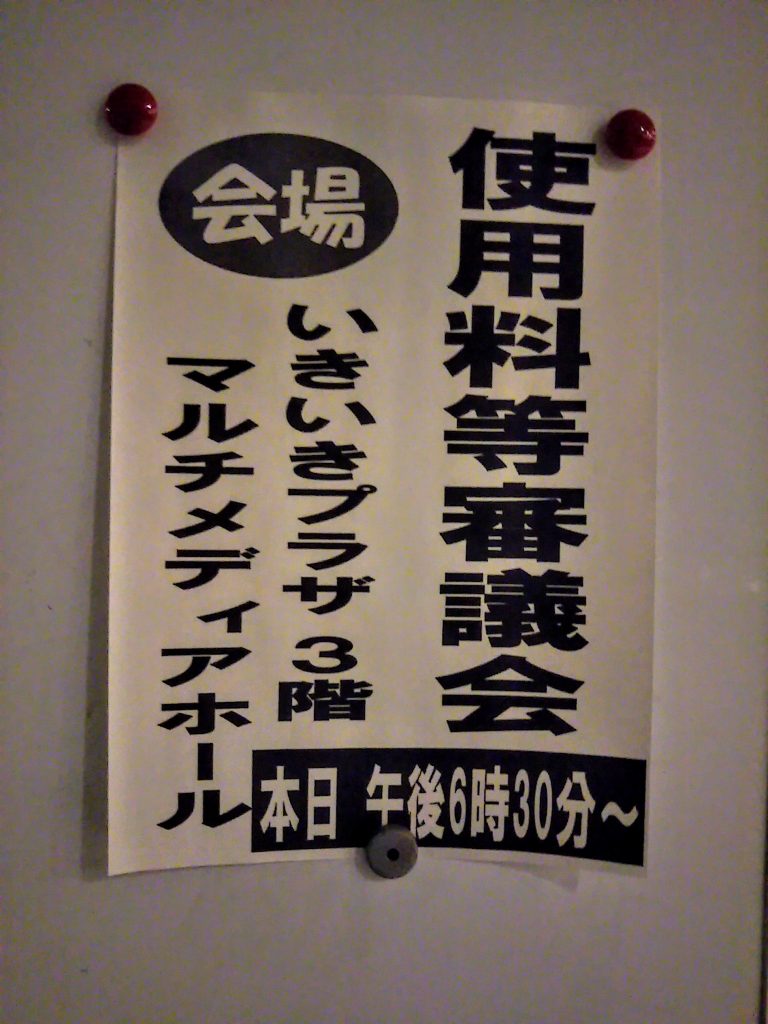
















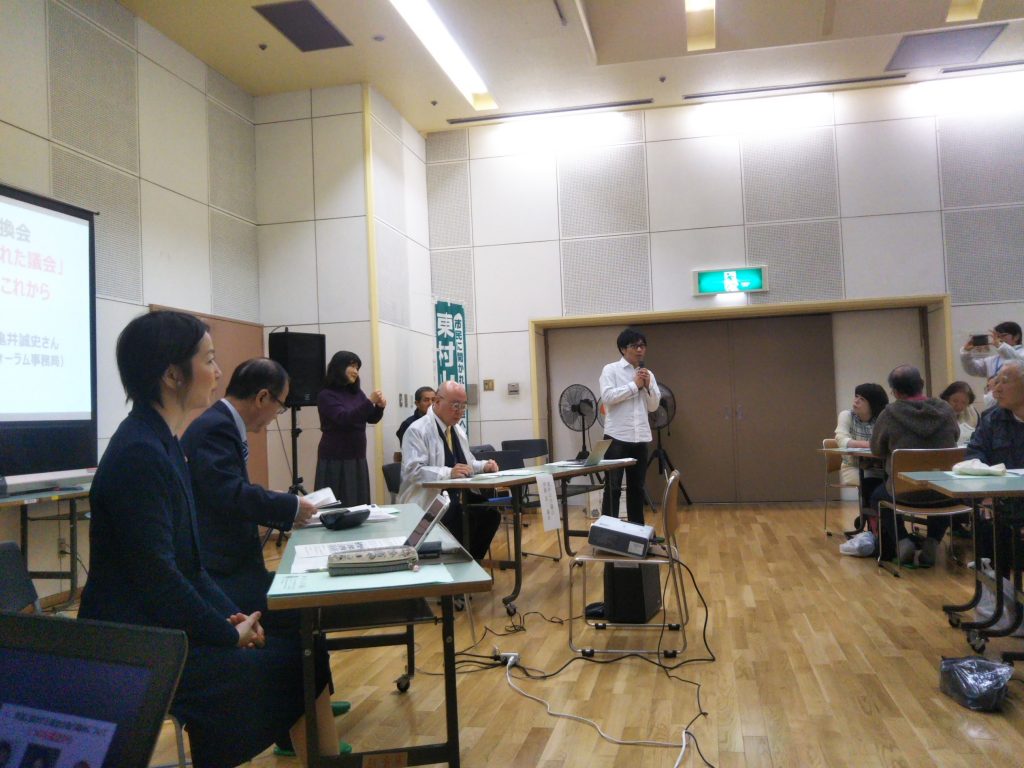

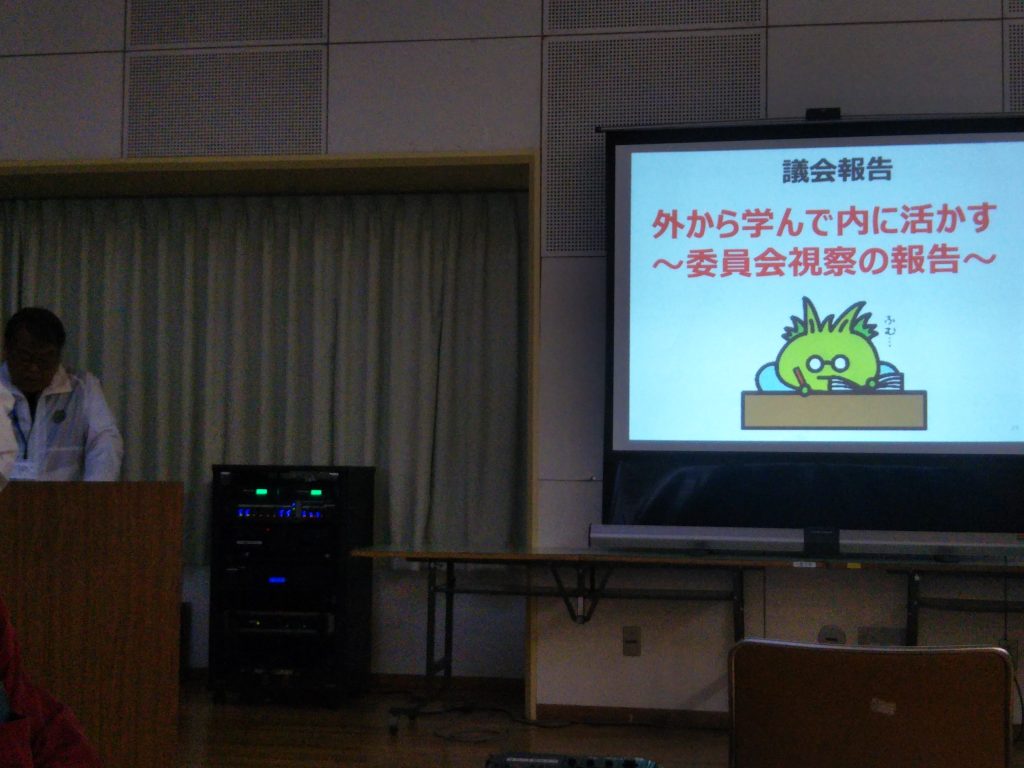



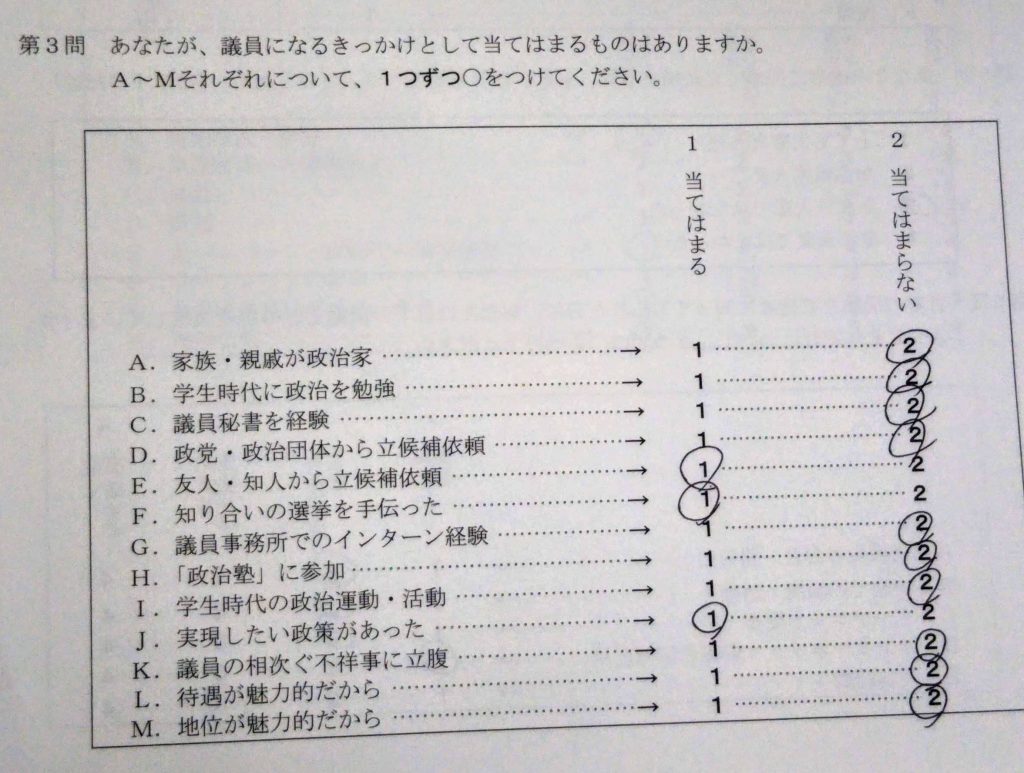
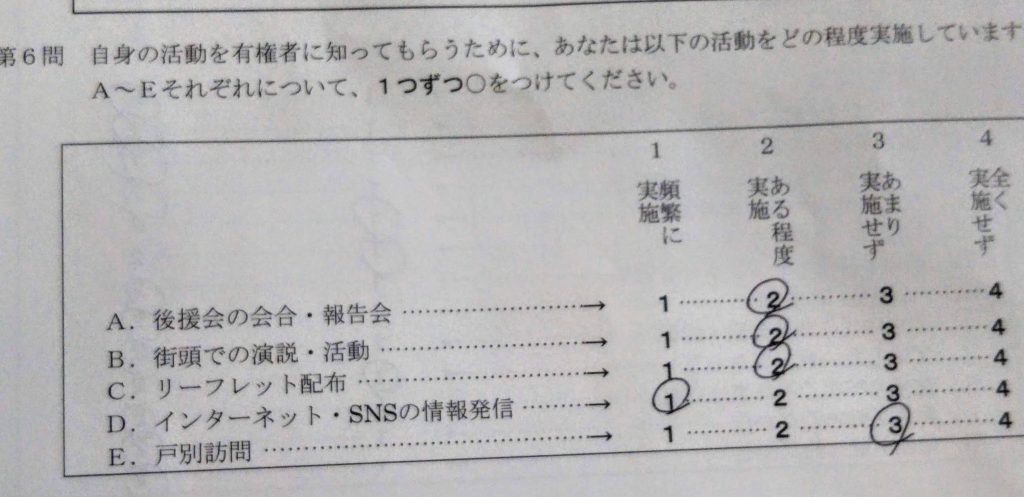
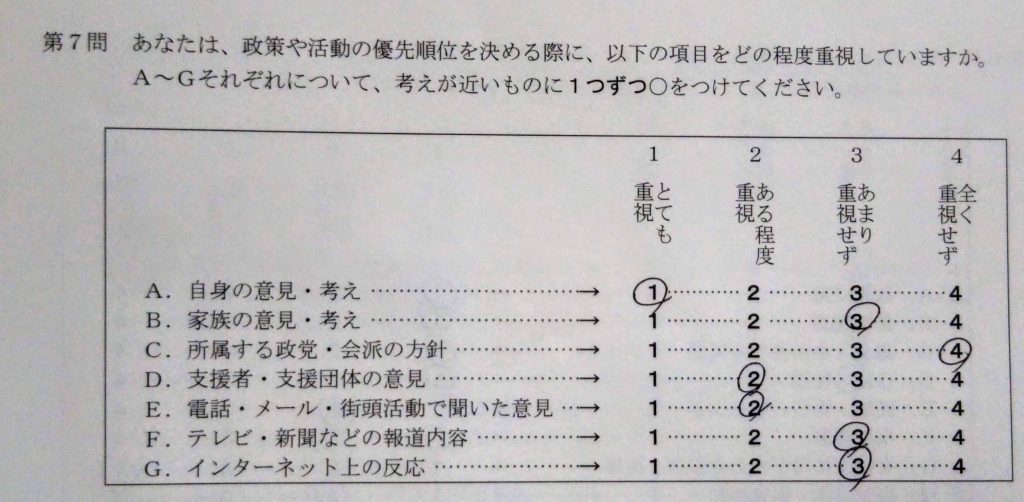
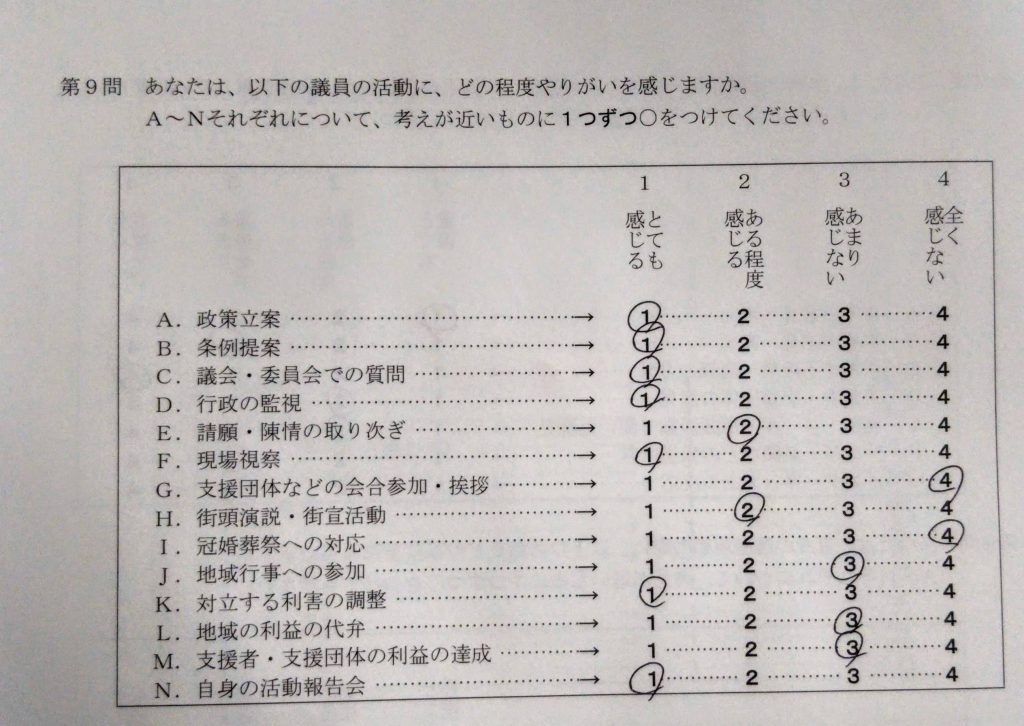
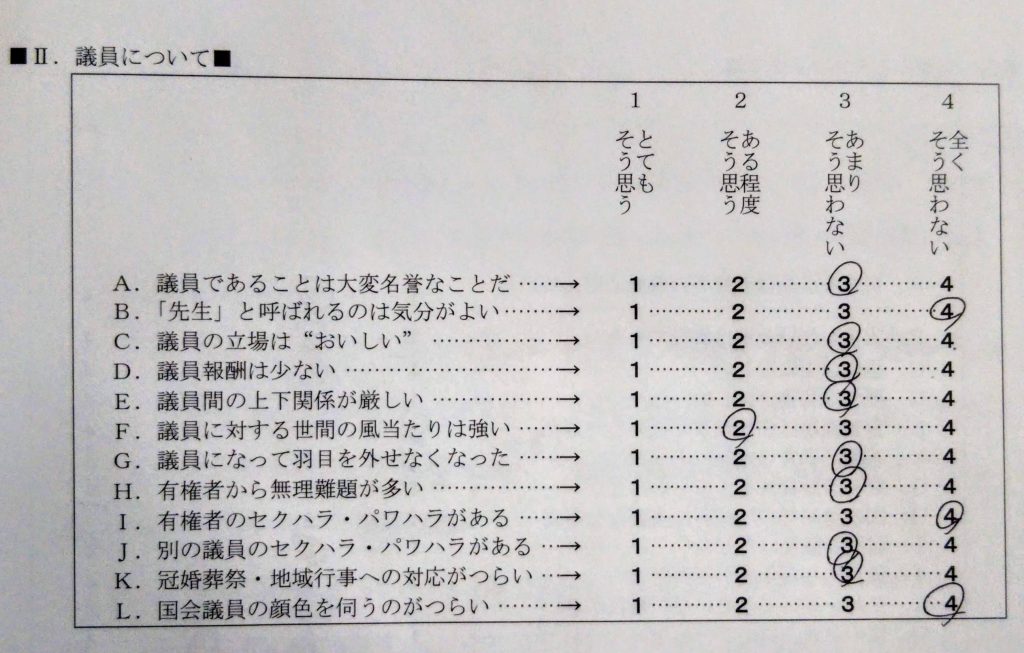
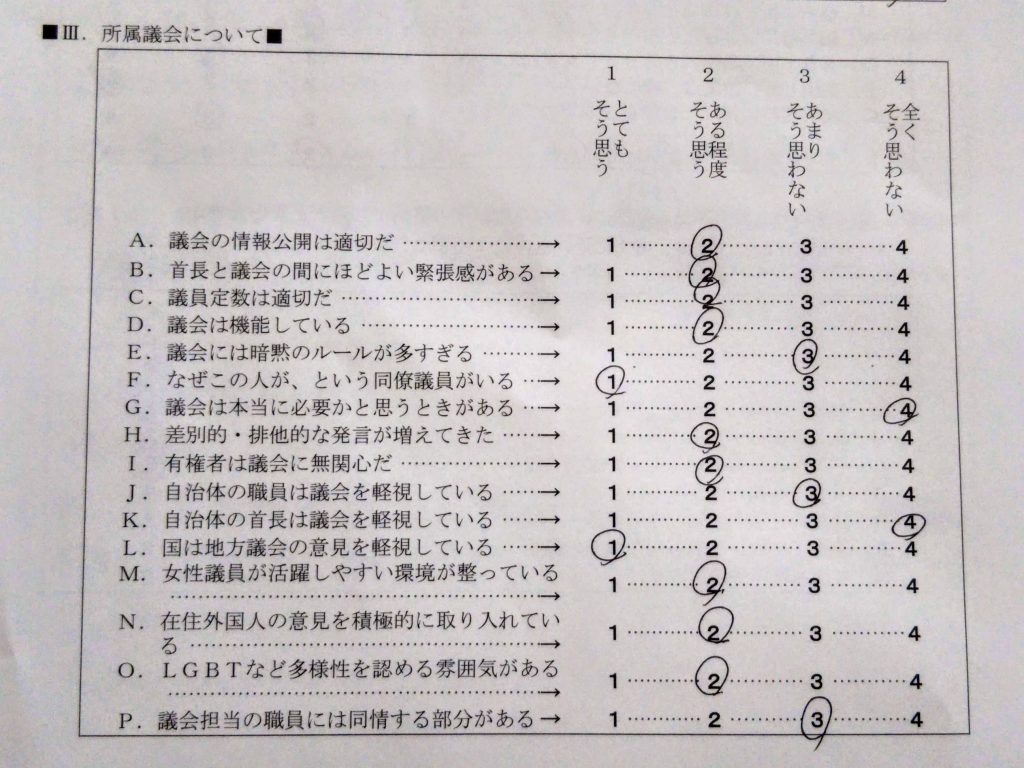
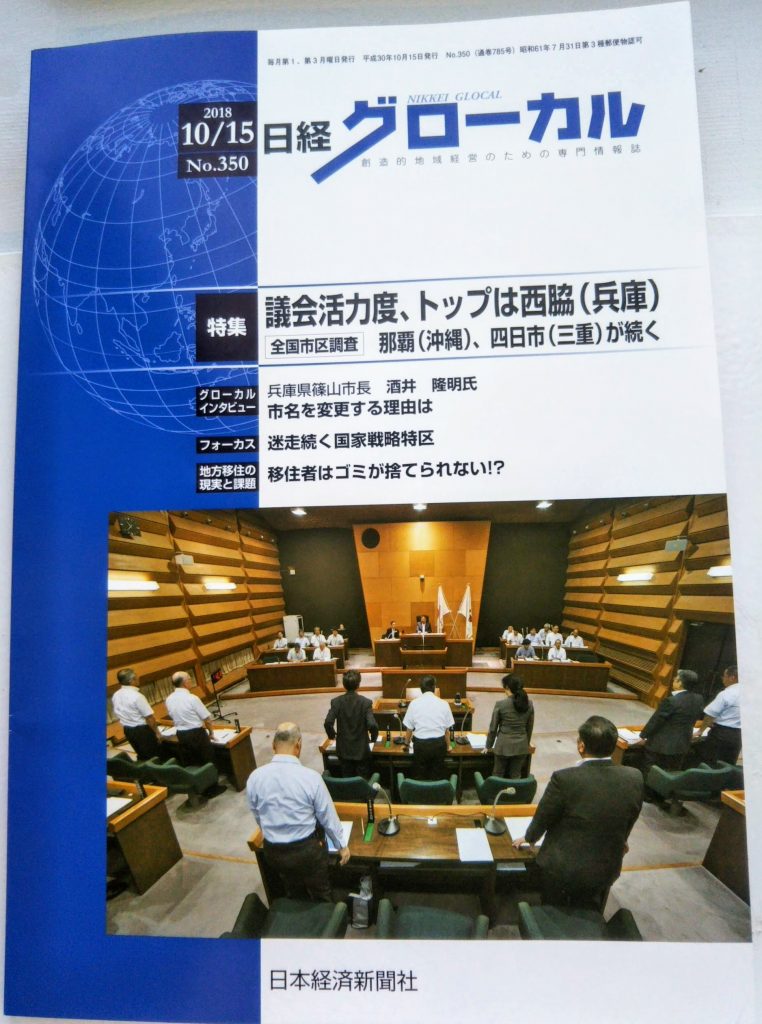
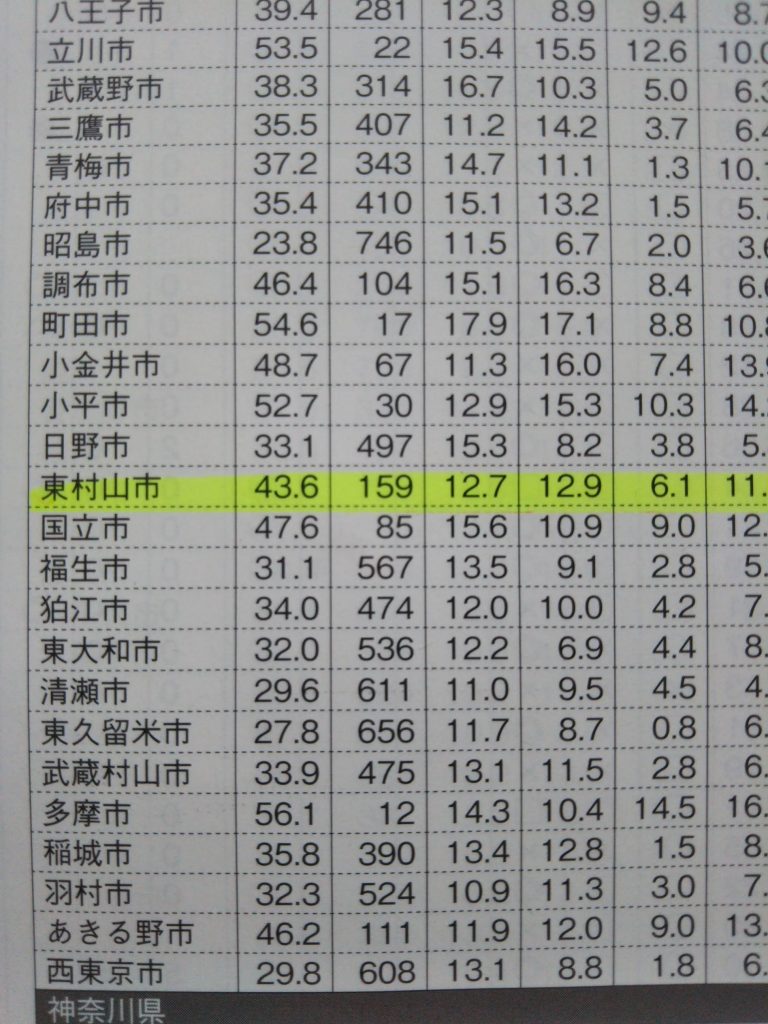

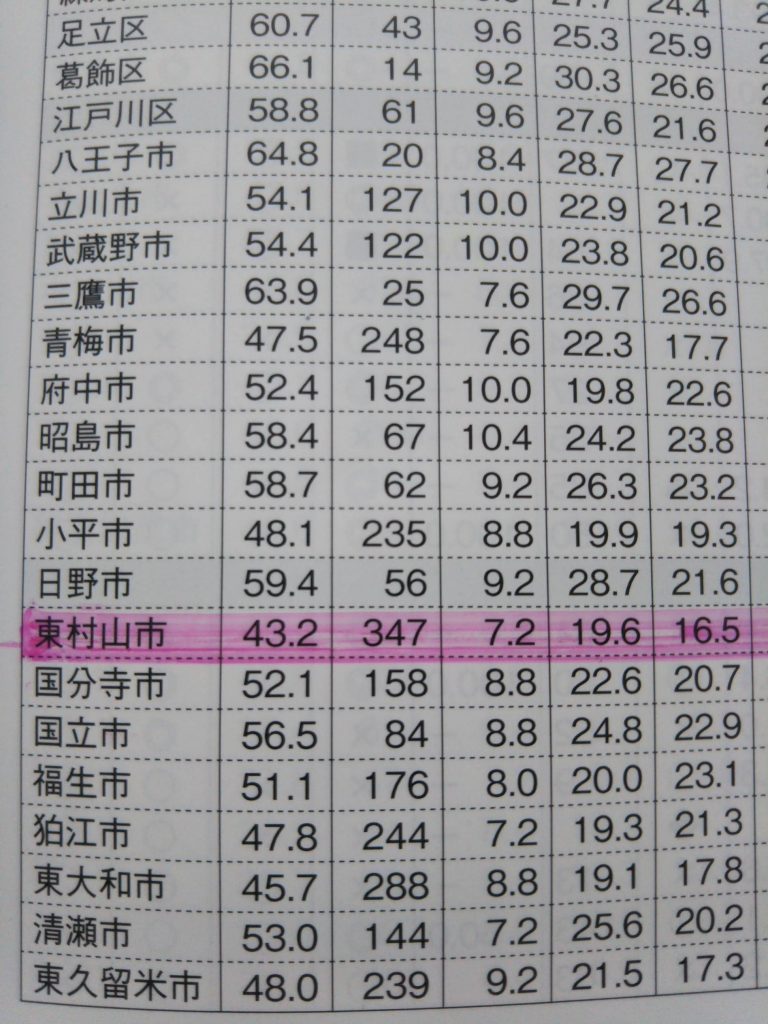

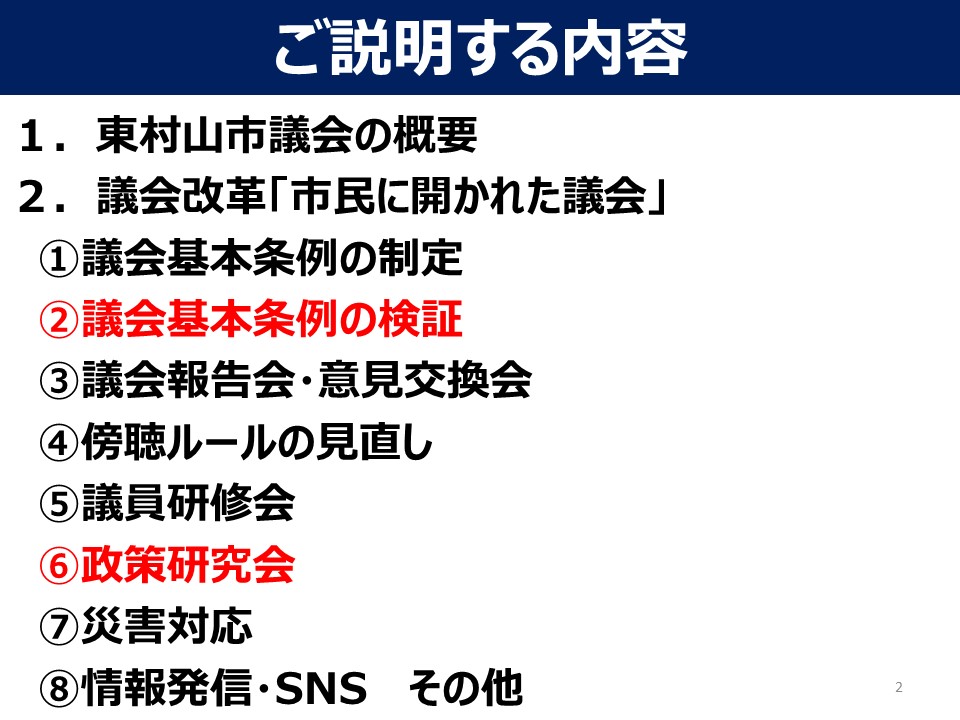

モノクロ-P.2-212x300.jpg)
P.1モノクロ-212x300.jpg)


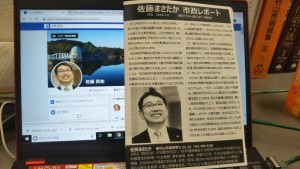
モノクロ-212x300.jpg)